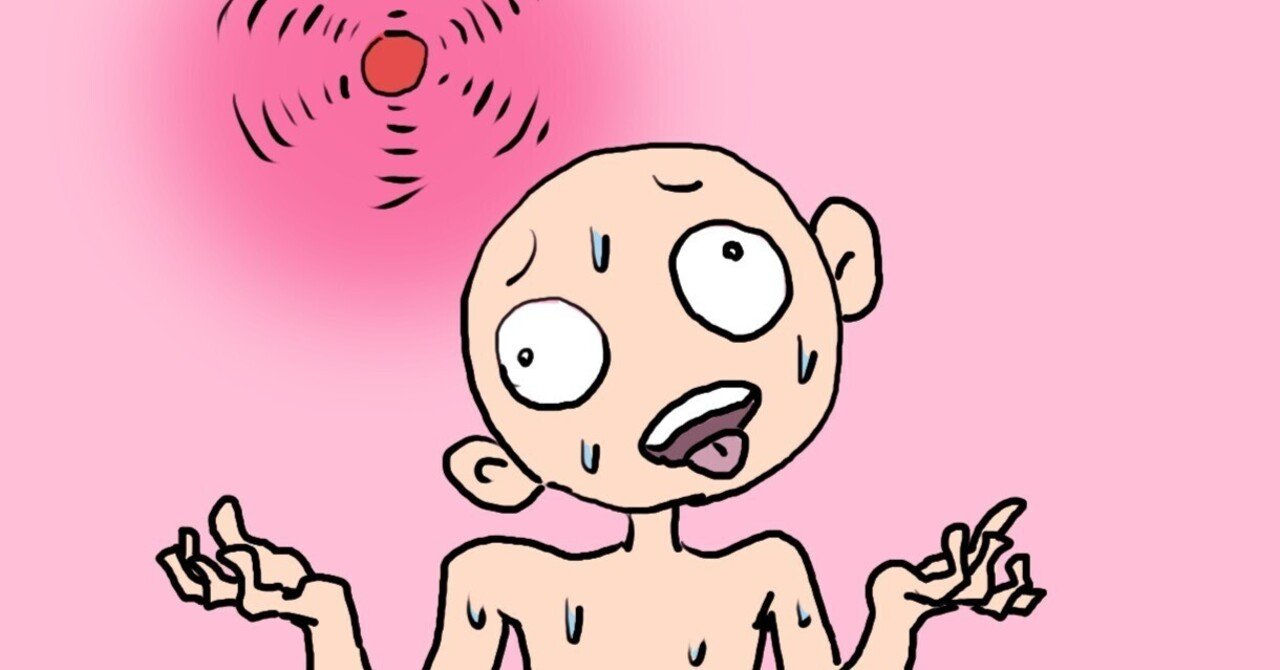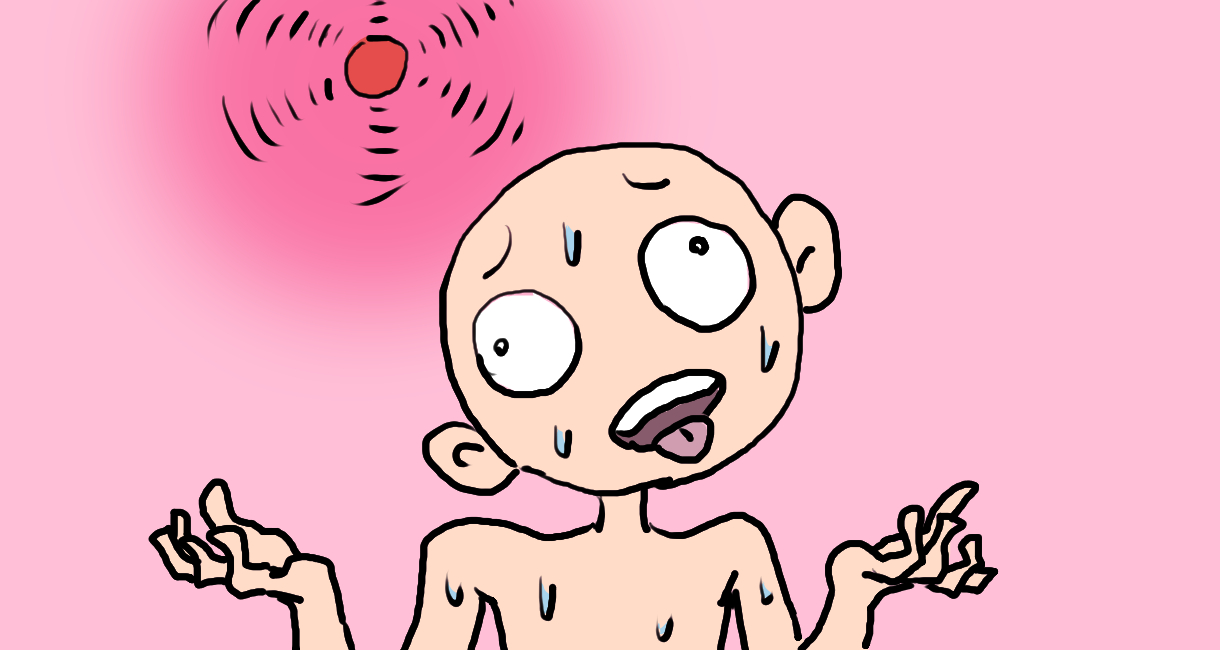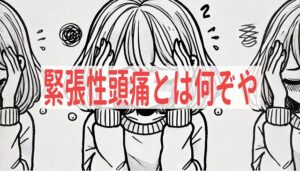さて、7月も半ばになり、当院でも「腰もそうだけど、夏バテには気を付けて下さいね」などという、定番のお見送り挨拶が日々繰り返されています。
が、この何気なく使う「夏バテ」という現象を注視して、言語化したことがないなと、ふと思ったのですね。
なんとなく倦怠感、食欲不振などが続くものと認識はしていますが、そのメカニズムを、つらつら述べられるかと問われれば、自信がないなぁ~というところ。
なので、今回は夏バテについてチョットだけ詳しく述べていきます。
夏バテとは?
夏バテとは、高温多湿な環境が続くことで、体の自律神経や水分・栄養バランスが乱れ、全身のだるさや食欲不振、疲労感などの不調を引き起こす状態のことを指します。
ちょっと面白いのは、この「夏バテ」。実は医学的な病名ではなく、日本独自の「季節性体調不良」にあたる概念だそうです。
夏バテのメカニズム(4つの主因)
次に夏バテのメカニズムについてですが、調べてみると以下の4つの原因が出てきました。
① 自律神経の乱れ
冷房と屋外の温度差により、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、内臓の働き・体温調節・血流が不安定に。
② 体温調節機能の疲弊
大量の発汗で水分・ミネラルが不足し、代謝エネルギーが低下。熱がこもりやすくなる(=熱中症一歩手前)。
③ 胃腸の冷えと機能低下
冷たい飲食の摂りすぎ+ストレスにより、消化吸収能力が落ちる。食欲低下→栄養不足の悪循環へ。
④ 睡眠の質の低下
熱帯夜により深い睡眠がとれず、疲労回復・自律神経の調整が妨げられる。
高温多湿の外気温で大量の発汗でミネラル・水分が失われてしまっている状態のところに、室内は冷房でキンキンに冷えている。そこに冷たい飲食で内臓も冷やし自律神経が乱れてしまう。
乱暴に言うなら「外は熱いのに中は冷たいというギャップが、自律神経を乱し、夏バテを引き起こしてしまう」という感じでしょうか?
続きはこちら