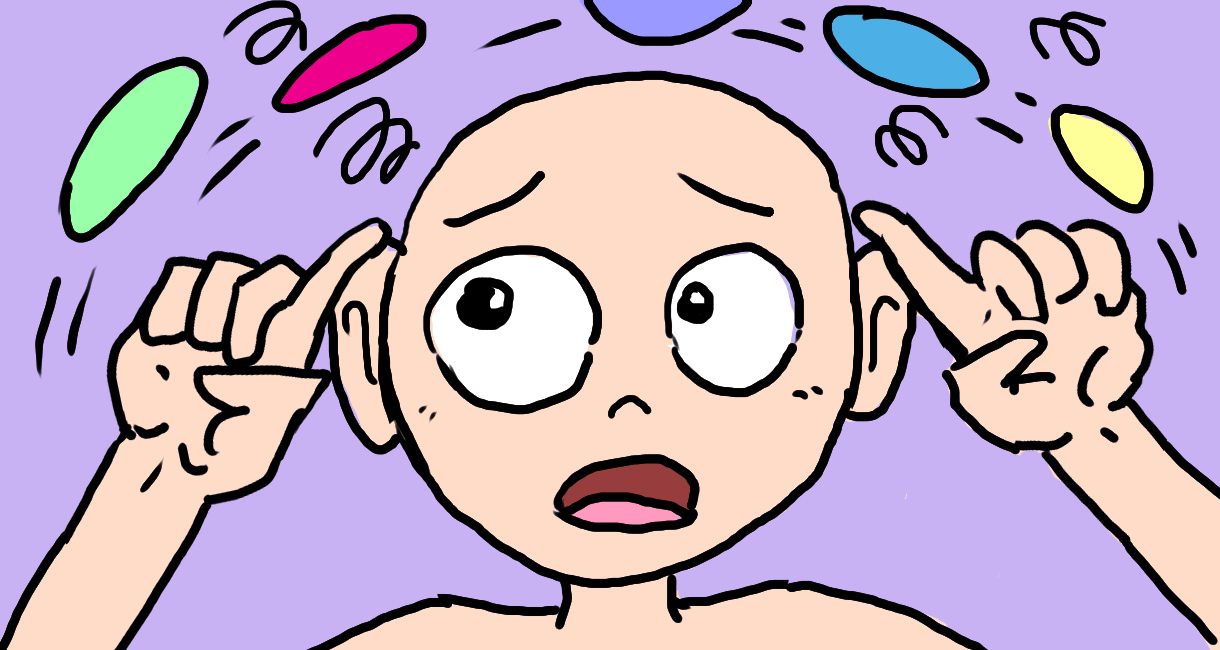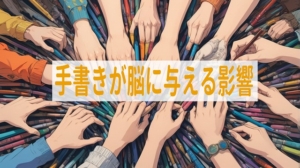ふと気がつくと、同じことを何度も考え続けてしまう。 気をそらそうとしても、またいつの間にか同じ思考に戻っている。
このような状態は心理学で「反芻思考(rumination)」と呼ばれ、 不安や恐怖、後悔といった感情をきっかけに起こりやすくなります。
反芻思考は性格の問題ではなく、 脳の危険検知システムと自律神経の働きが関係して起こる現象です。
反芻思考とは
反芻思考とは、過去の出来事や不安な出来事を何度も繰り返し思い出し、 頭の中で同じ考えがループし続ける状態を指します。
本来、脳は「もう終わった出来事」を過去として処理する仕組みを持っています。 しかし強い不安や恐怖の体験があると、 その出来事を「まだ危険が続いている」と誤認したまま記憶を再生し続けてしまいます。
その結果、思考が止まらず、安心できない状態が長く続いてしまうのです。
反芻思考のとき、脳では何が起こっているのか
反芻思考に関係する主な脳の部位は、 扁桃体(へんとうたい)と前頭前野です。
扁桃体は「危険かどうか」を瞬時に判断する警報装置のような役割を持ち、 前頭前野は「本当に危険なのか」「どう行動すべきか」を冷静に判断する司令塔の役割を担っています。
強いストレスや不安が続くと、扁桃体が過剰に興奮し、 前頭前野のブレーキがうまく効かなくなります。
すると脳は「もう終わったはずの出来事」を、 まるで今まさに起きている危機のように扱い続け、 思考がループしやすくなってしまいます。
なぜ反芻思考は「ふとした瞬間」に始まるのか
反芻思考が起こりやすい背景には、 デフォルトモードネットワーク(DMN)という脳内ネットワークの働きがあります。
DMNは、ぼんやりしているときや何もしていないときに活発になる回路で、 内省や記憶の再生、自己のストーリー構築などに関わっています。
この回路が過剰に働くと、 思考が「今ここ」から離れ、「あのとき」「もしも」の世界へ入り込みやすくなります。
その結果、何気ない移動中や作業中に、 いつの間にか反芻思考が始まってしまうのです。
なぜ反芻はやめられなくなるのか
反芻思考が厄介なのは、 単に苦しいだけでは終わらない点にもあります。
脳の報酬系である側坐核は、 「意味づけができた」「納得できた」と感じた瞬間に、 わずかな安心感や快感を与えます。
反芻している間、 私たちは無意識のうちに「答え」や「整理」を探し続けています。
こうして反芻は、脳の学習回路として固定化されていきます。
反芻思考のループから抜け出すヒント
反芻思考を「やめよう」「考えないようにしよう」とするほど、 かえって強まってしまうことがあります。
大切なのは、別の脳回路へ意識を切り替えることです。
- 軽い運動やストレッチで身体感覚に意識を向ける
- 深い呼吸や瞑想で神経の興奮を鎮める
- 書き出す・話すことで思考を外在化する
- 五感を使った体験で「今ここ」に戻る
反芻思考と身体の緊張の関係
このような脳の状態が続くと、身体にも影響が現れます。
脳が警戒モードに入り続けていると、自律神経は交感神経優位の状態が続き、 呼吸は浅くなり、首や肩、背中の筋肉は無意識に緊張しやすくなります。
当院では、この状態を単なる筋肉の問題ではなく、 「過緊張状態」として捉えています。
補足:身体から整えるという視点
反芻思考の背景には、 脳だけでなく自律神経や身体の緊張状態が深く関係していることがあります。
そのため、思考だけでどうにかしようとせず、 呼吸や身体の緊張を整えることが、 結果的に頭の働きにも影響するケースがあります。
頭で考えすぎてしまう状態が続いている方は、 「身体から整える」という視点もひとつの選択肢として覚えておいてください。
.jpg)